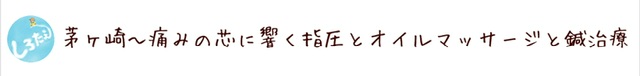精油と漢方、処方薬の違い
私達は病気の治療や未病治に精油(アロマオイル)を使ったり、漢方薬や薬を病院や薬局で購入して使うことがあります。
どれが効く、どれが効かない、諸説ありますが、それぞれ作用の仕方が違うので結局は自分のQOL(生活の質)にあったものを取り入れるのが一番効果的です。
精油の作用
精油はアロマテラピーで使われる、植物の有効成分を凝縮したものです。凝縮しているからこそ希釈して使う必要がありますし、強く効くため禁忌もあります。
精油は鼻から吸ったり、皮膚から吸収されて体内に入っていきます。
体内に入った後は血液に乗って肝臓で分解、最終的に代謝されて体外に出ていきます。この『代謝』というのがポイントで、体のどこかに留まるのではなく出ていってしまうために効果のほどが感じにくいのです。
しかし、代謝されてしまうということは各臓器を経由するということ。巡る間に要所要所でバランスを整えていきます。通りすがりに植物の有効成分で補ったり、排出を促すイメージ。長期的に使用することで美容と健康に貢献します。
漢方薬の作用
漢方薬は体力の有無、体質、さまざまなデータを加味して基本的にはお医者さんから処方されます。漢方薬の特徴として、同じ風邪を引いても子供か高齢者か?女性か男性か?体力が充実しているタイプか?などで薬が変わります。
薬局でも購入できますが、的外れな漢方薬を飲むと何も変わらなかったり具合が悪くなったりします。西洋の薬よりは効き目が穏やかですが。
効き目が穏やかなのは精油と一緒で、漢方薬も代謝されてしまうからです。その分、未病治の状態で飲んで体質改善などを目指すことができます。
処方薬の作用
最後に病院でもらうロキソニンなどの西洋の薬です。こちらは上の2つと違って体の中に蓄積しピンポイントで効果を発揮します。即効性があり、強い症状の時には待ってる時間などありませんからこちらが効果的です。
ロスバスタチンなどコレステロール阻害剤のように飲み始めたらずっと飲み続けないと元に戻ってしまうタイプの薬がありますが、こちらは肝臓や小腸でコレステロールの吸収を阻害する成分が入っているだけなので、飲まなくなったらまた吸収が始まるからです。
西洋の薬にしか助けられないこともたくさんありますが、その強さゆえに長期的に服用すると胃を痛めたり添加物の過剰摂取になり肝臓を疲労させたり副作用が大きいのもポイント。
このデメリットがメリットを上回る時に処方されます。基本的には。
最近ではパッチ型や舌下吸収型の薬を見かけますが、パッチ型は今アメリカなど海外で流行っているそうです。こちらは経皮吸収というルートを利用しているため、飲み薬のように即効胃で消化されないので効き目が長いとされています。
舌下吸収は粘膜吸収を利用しているので吸収速度が速く、パッチと同じく胃酸の影響を受けないというメリットがあります。
医学は日々進歩しているんだなぁと驚きますね。私の経験では、アロマセラピストを長くやっている人はやたら健康な人が多いです。毎日腕から鼻から吸収することで自然と整ってるんじゃないかと思っています。
コロナの時もさほど蔓延せず、風邪など滅多に引かない人が多いんですよね、接客業なのに。どちらかといえば手首や腰を痛めて辞めることが多いです。誰も気づいていないですが、私は他にも仕事をしているので統計的にそう感じることが多くて。
いかがでしたか?漢方薬や精油はいつになったら効果が出るのかわかりにくい反面、長期に服用しても悪い影響が起こりにくく、むしろ長期的に服用することでバランスのいい状態を作ってくれます。そして西洋の薬はいざという時に痛みを止めてくれる強力な味方。上手に使い分けて体のケアに役立ててくださいね!